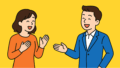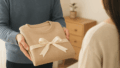お正月に欠かせない飾りといえば「鏡餅」。
でも
「どこに飾ればいいの?」
「飾り方の順番は?」
と迷ったことはありませんか?
実は鏡餅には飾り方の基本だけでなく
一つひとつに深い意味が込められています。
この記事では
初心者の方でもすぐに実践できる
鏡餅の飾り方と順番を中心に
飾る意味や時期、場所、さらに鏡開きまで
分かりやすく解説します。
正しい知識で鏡餅を飾り
気持ちよく新年を迎えましょう。
鏡餅の正しい飾り方と順番
用意するもの一覧
鏡餅を飾るときに必要なものは
まず餅そのもののほかに
飾りとして使う敷物や紙飾りなどがあります。
基本的なセットとしては
下に敷く「四方紅(しほうべに)」や「奉書紙」
その上に乗せる「三方(さんぽう)」と呼ばれる台
さらに「裏白(うらじろ)」「昆布」
「譲葉(ゆずりは)」といった縁起物の植物
そして餅を二段重ね
最後に「橙(だいだい)」や代わりにみかんを乗せます。
市販の鏡餅セットを購入すれば
これらが一式揃っていることが多く
初心者でも迷わず準備できます。
もしすべて揃えるのが難しい場合は
最低限として「二段の餅」と「橙」を用意すれば
形になります。
最近ではプラスチック製の容器に
切り餅が入った簡易型も人気で
長く保存できるのが特徴です。
用意するものが分かっていると
飾り付けの手順もスムーズに進められます。
下から順に並べる流れ
鏡餅を飾るときは、下から順に整えていくのが基本です。
まずは台となる「三方」やお盆を用意し
その上に「四方紅」や白い紙を敷きます。
その上に
「裏白」や「昆布」「譲葉」などを飾り
縁起を込めます。
その後
下に大きい餅、上に少し小さい餅を重ねるのが
基本の形です。
これは「月」と「太陽」を表しているとされ
円満や調和を願う意味があります。
餅を重ねたら、その上に「橙」やみかんを乗せます。
この順序を守れば、誰でも整った鏡餅が完成します。
市販のセットを使う場合も
パッケージに書かれた順番通りに並べれば安心です。
紙垂(しで)の置き方
鏡餅の飾りでよく見かける「紙垂(しで)」は
白い紙を折って垂らした飾りです。
これは神聖な場所を表すもので、神社でもよく目にします。
鏡餅に添える場合は
餅の下や三方の縁に差し込むように飾るのが一般的です。
上下の向きに特に決まりはありませんが
紙が内側に折れるように置くと
より丁寧な印象になります。
紙垂を使うと一気にお正月らしさが出て
神聖な雰囲気を演出できます。
橙を乗せる意味と位置
鏡餅の一番上に乗せる「橙(だいだい)」は
「代々(だいだい)栄える」という言葉にかけて
家族の繁栄や長寿を願う縁起物とされています。
本来は橙を使うのが正式ですが
スーパーなどでは入手しにくいため
みかんで代用する家庭も多いです。
位置は餅の中心に安定よく置くことが大切で
傾いてしまうと全体の見栄えが崩れてしまいます。
市販のプラスチック製セットにも
橙の形をした飾りがついており
気軽に取り入れられます。
市販のセットを使う場合の注意点
近年はスーパーやコンビニで
プラスチック製のケースに入った鏡餅が
手軽に買えます。
これらは中に個包装の切り餅が入っているので
飾った後にそのまま食べられるのが便利です。
ただし、紙垂や裏白などが
省略されていることも多いので
本格的に飾りたい場合は追加で用意するとよいでしょう。
また、ケースに入っているとはいえ
熱で内部が劣化することがあります。
「直射日光や暖房の風が当たる場所」を避け
涼しくて安定した場所に置けば、より安心です。
鏡餅を飾る場所の基本
一番多い置き場所
鏡餅を飾る場所で最も一般的なのは
「居間」や「リビング」といった家族が集まる空間です。
昔は「床の間」が定番でしたが
現代の住宅には床の間がないことも多いため
家の中心となる場所に飾るのが主流になっています。
家族が自然と目にする場所に置くことで
お正月の雰囲気を楽しめると同時に
「年神様をお迎えしている」という気持ちを持つことができます。
食卓やテレビ台など
安定感のある場所に飾る家庭も多く
形式にこだわらなくても十分に意味があると言えるでしょう。
神棚や床の間に飾る場合
神棚や床の間がある家庭では
そこに飾るのがより伝統的です。
神棚に飾る場合は
中央に置いて年神様にお供えする形になります。
ただし神棚は高い位置にあるため
餅や橙が見えづらくなることもあるので
見た目を意識するなら床の間もおすすめです。
床の間は古来から
客人を迎えるための格式ある空間とされ
鏡餅を飾るのにふさわしい場所です。
特に和室がある家庭では
お正月らしさを演出できる場として人気です。
リビングや玄関に飾ってもいい?
リビングや玄関も
鏡餅を飾る場所としてよく選ばれます。
リビングは家族が集まる中心の場なので
一番目につきやすく
「新年を迎える喜びを共有する場」
としてぴったりです。
玄関は
「年神様が最初に入ってくる場所」
と考えられるため
小さめの鏡餅を置くと縁起が良いと言われます。
最近では
玄関にワンポイントとして小さな鏡餅を置き
リビングには大きめの鏡餅を飾るといったスタイルも人気です。
台所に飾る意味
昔から「台所の神様(荒神様)」を
大切にする文化があり
台所に鏡餅を飾る家庭もあります。
火や水を扱う場所である台所は
家族の生活に直結する重要な場所です。
そのため小ぶりの鏡餅をお供えし
一年の無事を祈る習慣があります。
現代ではスーパーなどで
「神棚用」「玄関用」「台所用」といった
複数の小さな鏡餅がセットになった商品も販売されており
家の中のさまざまな場所に分けて飾ることができます。
神棚がない家での置き方
現代の住宅には神棚や床の間がないケースも多く
その場合は「家族がよく集まる場所」や
「清潔で安定した場所」に飾れば十分です。
例えば、リビングのサイドボードやテレビの横
ダイニングテーブルの一角などでも問題ありません。
大切なのは
「家の中で大事にされている空間に置くこと」
であり
形式に縛られすぎず
自分の生活スタイルに合った場所に飾るのが一番です。
市販の小型鏡餅なら
ちょっとした棚や机の上にも飾れるので
限られたスペースでも気軽にお正月気分を楽しめます。
鏡餅を飾る意味と由来
なぜお正月に飾るのか
鏡餅は、年神様(としがみさま)と呼ばれる
新年の神様をお迎えするために飾られます。
年神様はその年の豊作や
家族の健康を守ってくださる存在とされ
鏡餅はその神様の依り代(よりしろ)となるものです。
つまり、鏡餅は単なる飾りではなく
「神様の居場所」としての意味を持っています。
正月に鏡餅を飾ることで
一年の無病息災や
家族の繁栄を願う文化が生まれたのです。
鏡餅が丸い形をしている理由
鏡餅は二段重ねの丸い形が特徴的ですが
この形には深い意味があります。
まず「丸」は円満を象徴し
家庭が仲良く調和することを願う形です。
また、上下の二段は
「月と太陽」「陰と陽」を表しているとも言われ
自然の調和を願う意味合いもあります。
さらに「鏡」という言葉には
古代から神聖な道具としての意味があり
丸い餅の形が銅鏡に似ていることから
その名がついたともされています。
橙に込められた願い
鏡餅の上に飾る「橙(だいだい)」は
名前が「代々」とかけられており
「家系が代々栄えるように」
という願いが込められています。
本来は橙を使いますが
近年では手に入りやすいみかんで
代用する家庭も増えています。
どちらを使っても縁起を担ぐ気持ちは同じで
家庭の幸せや長寿を祈る心が大切にされています。
四方紅や敷紙の意味
鏡餅の下に敷かれる「四方紅(しほうべに)」は
四方を赤で囲った紙で
災いを防ぎ、家庭を守る意味があるとされています。
白い奉書紙だけを使う場合もありますが
赤が入ることでより厄除けの意味合いが強まります。
また、餅の下に飾る
「裏白(うらじろ)」はシダの葉で
裏側が白いことから「清浄」を表し
夫婦円満や長寿を願う意味もあります。
昆布は「喜ぶ」に通じ
譲葉(ゆずりは)は「家系の継続」を象徴するなど
一つひとつの飾りに願いが込められています。
昔と現代の違い
昔の鏡餅は家庭でついた餅を大きく作り
家の中心に堂々と飾っていました。
しかし現代では
生活スタイルの変化や保存の都合から
切り餅入りのプラスチックケース型が主流になっています。
形式が簡略化されても
「年神様をお迎えする」という本来の意味は変わりません。
現代的な形にアレンジしつつも
願いを込めて飾る心が一番大切だと言えるでしょう。
鏡餅を飾る時期について
飾り始めるのはいつ?
鏡餅を飾り始める時期は
一般的に「正月事始め」と呼ばれる
12月13日から準備が始まり
実際に飾るのは年末が多いです。
特に多いのは12月28日。
数字の「八」は末広がりで縁起が良いため
この日に飾ると良いとされています。
一方で、29日は「二重苦」を連想させ
31日は「一夜飾り」と言って
神様に失礼にあたるとされるため避けられています。
家庭によっては27日や30日に飾るケースもあり
あまり厳密にこだわらず
「年神様を迎える心構えができた日」
に合わせるのが良いでしょう。
避けたほうがいい日
避けるべきとされる日には理由があります。
29日は「九(苦)」がつくことから
縁起が悪いとされており
特に昔から敬遠されてきました。
また、31日は大晦日で
前日だけに慌ただしく飾るのは
「神様をおろそかにしている」と考えられ
「一夜飾り」として避けられています。
これらは迷信に近い部分もありますが
せっかくなら良い気持ちで新年を迎えるためにも
28日や30日に準備するのがおすすめです。
飾っておく期間の目安
鏡餅は、基本的に「松の内」と呼ばれる期間中飾られます。
松の内とは、門松を飾っている期間のことで
地域によって1月7日まで、または15日までと異なります。
その間は年神様が滞在していると考えられており
その依り代である鏡餅も
大切に飾っておくのが習わしです。
つまり、飾る期間は「年末から松の内が終わるまで」
と覚えておくと分かりやすいです。
地域による違い
関東と関西では、飾る日や片付ける日に違いがあります。
関東では1月7日までが松の内ですが
関西では15日までとすることが多いです。
そのため、鏡開きの日程も地域によって変わるのです。
地域の風習や家庭の習慣に合わせるのが自然であり
必ずしも全国一律でなくて構いません。
最近では
「子どもの冬休みに合わせて早めに飾る」
「仕事納めのタイミングで飾る」など
生活スタイルに合わせて柔軟に決める人も増えています。
片付ける日程の考え方
鏡餅を片付けるのは、松の内が明けたあとです。
関東では1月7日以降
関西では15日以降に片付けて
鏡開きの日に餅を割っていただきます。
飾りを外す際には感謝の気持ちを込め
「今年も家族を見守っていただきありがとうございます」
と心の中で思うだけでも意味があります。
形式だけにとらわれず
気持ちを込めて飾り
きちんと片付けることが大切です。
鏡開きとその後の楽しみ方
鏡開きの日はいつ?
鏡開きは
お正月に年神様をお迎えしていた鏡餅を
下げていただく行事です。
日程は地域によって異なり
関東では1月11日
関西では1月15日や20日に行うことが多いです。
この違いは松の内の長さに由来しています。
鏡開きの日は
「年神様がお帰りになったあと」に行うのが基本で
その餅をいただくことで
「神様の力を分けてもらう」
という意味が込められています。
包丁を使わない理由
鏡開きでは「包丁を使わずに割る」のが習わしです。
これは武士の時代
刃物を使うことが「切腹」を連想させるため
避けられたことに由来します。
代わりに木槌や手で割るのが一般的で
「割る」ではなく「開く」と表現するのも
縁起を担ぐためです。
固くなった鏡餅は扱いにくいですが
電子レンジで少し温めたり
袋に入れて金槌で軽く叩いたりすると割りやすくなります。
おしるこや雑煮などの定番料理
鏡開きで割った餅は
そのままでは硬くて食べにくいので
調理していただくのが一般的です。
定番は「おしるこ」や「ぜんざい」。
甘い小豆と一緒に煮ることで柔らかくなり
体も温まります。
また、地域によっては
「雑煮」に入れて食べる家庭も多いです。
出汁に溶け出したお餅は香ばしく
正月気分をもう一度味わえる一品になります。
保存方法と注意点
割った餅を一度に食べきれない場合は
小分けにしてラップで包み
冷凍保存するのがおすすめです。
冷凍すれば1か月程度は美味しく食べられます。
解凍は
電子レンジかオーブントースターで加熱すれば
すぐに柔らかくなります。
ただし、カビが生えてしまった餅は
食べないようにしましょう。
鏡餅は神様にお供えした大切なものですが
無理をして体を壊しては元も子もありません。
食べられる部分を感謝していただくことが大切です。
最近人気のアレンジレシピ
最近では、鏡餅を洋風にアレンジして
楽しむ家庭も増えています。
例えば
ピザ用チーズと一緒に焼いて「餅ピザ」にしたり
ベーコンで巻いてフライパンで焼いた
「餅ベーコン巻き」も人気です。
さらに揚げ餅にして塩や醤油をまぶせば
おやつやおつまみにもなります。
こうしたアレンジを取り入れることで
最後まで美味しく食べ切ることができます。
伝統を守りながらも
自分たちの食生活に合わせた工夫をするのも
現代ならではの楽しみ方です。
まとめ
鏡餅は単なる正月飾りではなく
年神様をお迎えし
その力を家族に分けてもらうための大切な行事の一つです。
正しい飾り方の順番は
「敷物 → 縁起物 → 二段の餅 → 橙」とシンプルで
市販のセットを使えば誰でも簡単に整えることができます。
飾る場所はリビングや玄関、神棚など
家庭に合った場所で大丈夫です。
意味や由来を知ることで
お正月の飾り付けが
より特別なものに感じられるでしょう。
飾る時期は年末の28日や30日が良く
片付けは松の内が明けたあと。
鏡開きでいただく餅には神様の力が宿るとされ
定番の雑煮やおしるこはもちろん
アレンジレシピでも美味しく楽しめます。
形式にこだわりすぎず
感謝の気持ちを込めて飾り
いただくことが一番大切です。
今年はぜひ、意味を知ったうえで鏡餅を飾り
家族でお正月を楽しんでみてください。